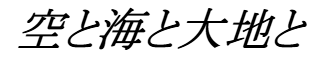追記。職業と語り 職業の語り
自営業には定年がありません。そのかわり 65歳になっても70歳になっても たぶん80歳になってもやめられない。人手不足ですしね。猫の手よりはマシ......いくつになっても容赦なくこきつかわれる.....というか 自分で 自分をこきつかう。電話の応対 接客 見積書作成 クレーム処理 電話連絡と確認 社員さんの送り出しと出迎え 入院している社員 以前在籍していた社員さんへのお見舞い 叱咤激励 顧客への挨拶 やってもやっても 仕事はつきない。
仕事に追われながら 25年 語りをつづけてきました。夜寝る間もなく 台本を書き 展示する資料をつくり ものがたりの背景をまなび 歴史をしらべ 声楽を学び 演劇を学び ...ひまをみてはワークショップに出かけた......それは 苦労ではなかった。むしろ 仕事から離れる時間が持てたことは 幸いでした。
しごとにプラスになったことも多かった コミュニケーション力 会話から相手の目的を察知する推理力 ..... そしてしごとが語りにプラスになったことも多くある。瞬発的な現場の把握 たちどころに問題点が見えること 段取り 構築力 場の支配 時間がないので その場で語るしかなく 即興で語れるようになったこと ほかの語り部さんの語りを聴いて すぐ語れること (但し いい語りのとき)
時間がないことは 武器に 強みになる 相互が より合わさって 切れない つよい綱になる。
一方で 職業的語り部はいるのだろうか? 噺家 イエス。ナレーションは? 原稿を読みながらはちょっと違う。司会業は これもちょっと違う。海外では プロのストーリーテラーがいる。ハープやギターを手に語るひともいるし とにかく ものがたりを語ることで生計を立てているひとが今も現実にいる。昔は日本にもいたのです。ゴゼさんとか 琵琶法師とか 浄瑠璃語り .....。それらのひとたちは 娯楽の少ない時代 村人たちが待ち望む エンターティナーとして 旅をしながら門付けをしたのです。
もともと 歌と語りは 同じルーツをもっていました。ウツ カツが うたう かたる の古語と関敬吾先生はおっしゃいます。 双方とも ひとの魂を揺さぶるモノでした。巷の語り部たちは 弦楽器や打楽器によって 聴き手のひとびとをトランス状態にすることができ..... ひとびとはものがたりに没入し陶酔し 泣き 笑いました。
今 日本の 語り部たちは 細々と 学校などで語っています。けれども 語り部たちが 素話などという言葉を棄てて 生き生きと語りだしたなら ことたまのさきわう国 日本は変わってくる 実は ラッパーたちは末裔のひとりなのかもしれません。
(俳優さんでチケットを売って語りをするひとは今の日本にもいます。けれど テキストを手にしながらのそれを語りとはわたしには思えないのですね)