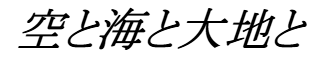子どもたちの戦争 語り手のなかにないものは つたわらない
小学校5年生・6年生に向けた「子どもたちの戦争」の台本に 苦心惨憺の日々です。1時限のなかで 5つのエピソードでつづってゆく 太平洋戦争 子どもたちとディスカッションしながら進める 「子どもたちの戦争」は 15年かけてつくりあげてきたカタチで何パターンかの定番があった。 その定番とおりなら 1日練習 1日リハ そして本番でいけるのだが 今年度は それぞれの学校にあわせて 中学も含めると6通りのあたらしい台本が 必要だった。
定番とおりにできない一つの理由は 著作権である。
子どもたちには 太平洋戦争の全体像 歴史を知っってもらいたいし 戦争の中で 聴いてくれる子どもたちと同じ年代の子どもたちが 戦争をどう生きたか あたまでなく感覚でからだで感じて できうれば 戦争をともに生きてもらいたいのである。しかし残念なことに 地元のひとの体験談『口承』には ヒロシマ 沖縄 満州についての体験がない。そこである部分は 書籍からの『書承』に 頼ることになる。ヒロシマの少女のエピソード それは原爆の悲惨さだけでなく ひとのこころのうつくしさが感じ取れる子どもたちにぜひ聴いてもらいたいものがたりだった。
学校関係は著作権の埒外なのだが 新聞社の記者さんが動画をつくってくださるというので 出版元のD社におうかがいを立てた。すると わずか1分のエピソードに 出版社 本の名称 作文を書いた少女の名前 挿絵画家のいわさきちひろさんの名前が入ったテロップを入れてくれという。とても無理なので あきらめてわたしが採話したエピソードと組み替えた。著作権は書いたひと/描いたひとの当然の権利である。しかしながら 作文を書いた少女もいわさきちひろさんも 今を生きる子どもたちに つたえてほしいと 願っていると思う。ひたひたと不穏な足音がちかづいてくる この時だからこそ。 戦災で亡くなったたくさんの子どもたちも 気が付いて!と ささやいていると思う。でも
しかたがない それならそれで やり方を換えるだけだ。
けれど「子どもたちの戦争」を伝えるにあたり さらにひとつの障碍があった。2回目の読み合わせを聴いて わたしは首をかしげた。痛くない!? 寒くない!? 怖くもない。痛切な悲しみもない。妙にあかるく 妙に淡々としている。集団疎開から脱走した男の子が殴られているのに? 動物園の動物が殺されているのに? 文字面だけのうすいグレーの悲しみのようなもの...... グラマンが襲撃してくるのに? 粟立つような恐怖もない。 どうして.....
そこで エピソードのなかの共通するワード できごとを ピックアップしてみる。10のエピソードにほぼ共通するのは 「空腹」「空襲」「死」であった。
感情はどうかというと 「恐怖」はほぼすべてにあった。「悲しみ」「怒り」「不安」「痛み」もあった。......では エピソードの子どもたちは その恐怖や不安や悲しみと どう戦って生き抜いたのか?
「愛」「共感」「生き抜こうとする勇気」「ちいさな達成感」そして「希望」
では メンバーの読み合わせに なぜ その響きが ないのだろう?
わたしはささやかな実験をしてみた。 エピソードをホワイトボードに書いて その隣に どんな感情があるかメンバー 書いてもらった。
エピソードによって 空欄があった。感情のワードがたくさん書き込まれているのは 完成されたエピソードだった。
「恐怖」はなかった。「怒り」も なかった。
語り手のなかにない感情 語り手が読み取れない感情は 聴き手に つたわりようがない そこに無いのだから。
思うに メンバーたちは みな やさしい心の持ち主なのだ。.....だから やさしさ 希望とは 書けても 恐怖 怒り 死 は 心とからだが拒否するのだろう。
だから空虚な文字 による音声であらわすのであり からだとこころが発する響きでないから記憶にもとどまらないのだ。
わたしの好きなことばに 闇はひかりの左手 がある。アーシュラK・ルグインのSF小説のタイトルでもあり 陰陽をあらわす。
ネタバレになるので 書かないが わたしの思う 闇はひかりの左手 とは 「闇があるからこそひかりが耀く」である。
恐怖 怒り 死 という 闇が あるからこそ ひとのこころの輝き 愛 思いやるこころ 希望が 耀くのである。
わたしは 「子どもたちの戦争」を そのようなものがたりにしたい。気づかせてくれた仲間たちに感謝し ともに子どもたちに届けたい。
」