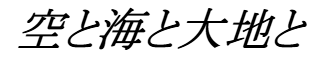ホワイトアウト/改稿/改稿
今日は『子どもたちの戦争』の本番でした。9:30に現場に入りセッティング ライト調整 からだをつくり 場当たりをして 2公演 5年生 6年生 とてもよく聴いてくれました。5年生は質問にも手があがりハキハキと答えてくれました。戦争が起きても災害が起きても 絶対生き延びる と思う人は手を挙げてと質問したら 6.7割が手をあげました。『森さんは 戦争体験者 数十人の方から おはなしを聴いたけど おかあさんに会うまでは とかふるさとに何があっても帰る と思ったひとは 生き延びるみたい....』といって もう一度訊いたら ほぼ全員 手をあげてくれました。教室に戻るときはひとりひとりが ありがとうございます と頭を下げて去ってゆきました。
二時間半の休憩のあと 6年生 6年生はほとんど手が上がりません けれど 指名すると答えてくれます。心の深いところでは さまざまな想いが生まれ交錯しているのでしょう。国とは みなさんも含め 国民と 街 山 川などの国土です。 みなさんの手で 国の平和を 守ってください 世界の平和を みなさんの未来を守ってください。 みな 手をあげてくれたと思います。
しかし わたしの心のなかでは 日本の置かれた状況 対中国のアメリカの盾日本 中国にとっても対アメリカの防波堤たる日本 を思い浮かべていました。15年前 語り継ぐ戦争と平和を 子どもたちにむけて伝えはじめた頃 戦争は目の届かないほど遠くにありました。これからを生きてゆく子どもたちの頭上には ブラックフォークのような戦争の黒い翳がほの見えます。2000年のコロナから世界は震撼し 世界各地でありえない災害 火事 地震 飛行機事故が起こり 経済は混乱し 指導者たちは迷走し さらに戦争の火の手があがり あたかも世界は凶暴な手でスガタカタチを強引に変えられようとしているかのよう......以前のように 闊達には語れなくなりました。その気持ちは子どもたちに届いているのだろう 子どもたちも 社会の動きや 直感から 漠とした不安を感じているかもしれない。少しでも背中を押してあげるような語りができただろうか..... 太平洋戦争で亡くなった 戦災孤児 満州のひとびと B29の空襲で亡くなった数十万から100万のひとびとの遺言をこれからの子どもたちに伝えられただろうか ......撤収終わって16:00 ホワイトアウト.... 目もよく見えず 肢もおぼつかず やっとのことで帰りました。
5つのエピソードをナビでつなぐ それは 聴いてくれる子どもたちの様子を見ながら 応答しながら の即興にちかいものです。それで神経が擦り切れるのかな..... 自分の受け持つ語りは 『旅』のようなもの ナビとつながっているけれど 独立したひとつの世界 主人公の目で視る 感じる その主観と ナビの客観のせめぎあい。.... だから?
...... それでもと 思うのです。数年前まで 中学校で 2時間連続して 別仕立ての公演を幾度も させていただきましたが こんな風に 疲労困憊することはなかった。このごろ 終わって あぁしあわせだ 生きていてよかったと 感じることが少ない。なぜだろう。 社会や世情がわさわさと戦前に似かよってきたからかしら.........年齢かな 全体の力不足かな。......カタリカタリも 支えてくれていた中堅の方々が 昨年つぎつぎにあの世にゆかれ あるいはご不幸などで力を落とされ わたしのめぐりは わかいひとが増えました。昔のように 阿吽の呼吸というわけにはいかない。100%安心して託せない。わかいひとたちも次第に育ってゆく.... その過程なのでしょうけれど ..... 疲れは 澱のようにたまってゆく。
この1年 公演のたびごと アクシデントの連続でした。昨年1月のおなじ小学校の公演は 人間関係で追い詰められ 満足に立つこともかなわなかったし 3月の 『邂逅』 では 前日に食道炎で 吐き続け あわや入院 天の助けか なんとか開演。ボンボヤージュでは 声が出なくなりました。障碍があるにせよ 公演そのものは お客さまに喜んでいただき 無事に終わる それは こころあたたかいお客さまやカタリカタリのみなさんの支えがあればこそでした。.........いいパフォーマンスをするには 気力・体力です。体力があっての気力 おそらくは 体力以上のことをしようとしているのでしょうね。 わたしはやり方を換えなければなりません。
6つのプログラムをとおして 着実に進化の見えるメンバーがいる けれど カタリカタリのみなさんはもっとできる かような年寄りを頼らず 自分で自分の語る 場 を開拓することだと思います。語り部の志を持ち 語りが好きなら できるはず。パートタイムの語り部では 与えられる場所恃みの語り部では 独り立ちはかないません。昨年4月 教えることは やめたはずでした。 たった一年で 一人前の語り部になるのは至難と思う。けれど どうか急いでください。成長してください。わたしは語りを知った 9か月後には 語りの会を企画しチラシを作成し 仲間に声をかけ 「コア石響」でステージに立ちました。だれだって やる気があればできるはず。そして 今や わたしには時間があまりない 残りの時間 自分が 納得できる語り 語って 聴いてくれるひとたちとひとつになって あぁしあわせだなぁ と 思える語りがしたいのです。昨年 約束したように 自立した語り部の集団 ユニット・カタリカタリでありたい。
今日は読売新聞の記者さんが 八潮の崩落現場から 駆けつけてくださって 動画も撮っていただきました。短いですが 視てくださるかもしれない 全国の語り部のみなさんが このようなやり方もあるのだと やってみようかなと思って下さったら うれしいです。それは 戦争をせきとめる 力になるかもしれないから。