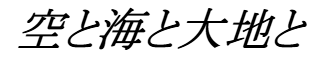つづき なにをもって語るか
きのうのつづきに 追加しました。
なにをもって 語るか .... は 語り手あるいは語り部 それぞれ 異なります。
都市の語り手の場合 ほとんどが 自らを癒す その希求であると 多くの語り手さんを 見て その語りを聴いて わたしは感じるのです。なかには こころから ものがたりが好きな方もいます。そして ほんとうにごくわずかですが 語りの本来の役目を感知し 語る方もおられます。語りは 本とはまったく異なる世界のモノです。そのルーツは 祈り 天とつながるモノでした。そして 天の聲をひとびとにつたえるモノであり つたえる チカラを 持つひとが シャーマン≒語り部であったのです。語りは捧げモノ でもありました。(モノとは見えない もののこと)
長い時を経て 語りは 部族の歴史を伝えるモノとなり また 天の法《のり》をつたえるのみならず 部族の則《ノリ》をつたえるモノともなりました。語り部とは特別のやくめを持ち ハレの語りをするものは尊敬を得ました。
しかしながら 天への捧げモノであった語りは 次第に 娯楽にカタチを変えてゆきました。中世においては 吟遊詩人が 楽器を携え 歴史上のできごとや悲恋を 宮廷で格式ある家で あるいは広場で路地で 語り 聴く人の涙を誘い カタルシスを あたえたのです。それは 日本でも同じでした。瞽女 また 琵琶法師たちが 三味線や琵琶をひきながら 上つ方の御前(ゴゼの起こりとも)で あるいは 辻で 語ったのです。それらの モノ語りは 活版印刷等により 物語となり 文学となり 本となりました。 その本からですね 都市の語り手たちは語っているのです。
わたしは 実は ひとつの発見をしました。きのうの会は 感動を呼ぶ つまり 泣かせる題材が比較的に多い語りの会です。技量 テクニック の高さがもちろんあります。 常連のお客さまのなかには 感動したい 無意識的にカタルシスがを求めている そういう方もおられるでしょう。ハンカチを目に当てる 目頭に指先をもってゆく方が見受けられる 嗚咽も聴こえてくる ..... わたしが 目にしたのは 3名でしたから それでどうというのではないのですが その三名の方たちは 『石のカヌー』では なぜか うとうととなさっていた .... なぜ? わたしは たいそう 驚いたのですが.....
あとで 納得もいきました。眠ってしまうというのは とても 気持ちのいいことなのです 語り手の聲の波動が 究極 聴き手を 癒したのでしょう。 つまり あたりまえですが 聴き手も語り手どうようさまざまな方がいらっしゃるということ 語りになぜ惹かれるか どんな語りに惹かれるか どんなものがたりが その方を癒すの また 刺すのか それぞれ 異なるということ ..... ひとりの語り手あるいは語り部が あらゆるジャンル (口承の日本の昔話 伝説 笑い話 悲恋 戦争体験 パーソナルストーリー 文学 童話) の 語りができればよいのですが そうもいきませんから グループで ガラ・コンサートで 語ることは できるだけ多くの聴き手に対応するという 意味があるのですね。
さて 泣かせるテクニックというのはあります わたしは語り部ですから 袖から透けて見えてしまう時がある そんなときものがたりの世界から 素にかえってしまう。これは ほんとうに興覚めで あぁ だまされてでも 泣きたいなぁ 気持ちよく 泣かせてくれないかなぁ ....... けれど 語りや芝居 のだいご味は 心臓に来るのです。 人生の摂理 運命 生と死 身もこころも 震わせられたい あぁ そんなとき 涙なんて出ない。出たとしても ぽっちり です。 やさしいおはなし 元気が出るおはなし どれも好きですが これが わたしの個人的な想い です。 ...... 子どもたちへ成った方へ 歳経た方へ 語ってまいりましたが 自分も そうありたい。語り部の名は忘れられても .....。聴き手の人生が変わるような 震えるような語りを 魂がとぶような語りを 生涯に幾度かは してみたい......